保護中: 【申込者限定】令和7年度健康づくり研究討論会 発表要旨等データ
- 2026年01月22日
- 新着情報, 健康づくりトピックス, 県が主催するACE関連イベントの情報
脳卒中は、ある日突然、あなたの毎日を変えてしまう病気です。
後遺症が残ることも多く、ご本人だけでなく、家庭や仕事に大きな影響を及ぼします。
脳卒中は予防できる病気でもあります。
高血圧、糖尿病、喫煙、運動不足といったリスクを減らすことで、発症の可能性を大きく下げることができます。
「自分のため」にはもちろん、「大切な人のため」にも、今 健康について、考えてみませんか。
今から始める小さな一歩が、あなたと、あなたの大切な人の未来を守ることに繋がります。
◇脳卒中デーとは?
2006年10月、南アフリカ共和国ケープタウンで開催された脳卒中国際会議で、国際脳卒中学会と世界脳卒中連盟が統合し、世界唯一の組織、世界脳卒中機構(World Stroke Organization, WSO)が結成されました。これを記念し、毎年10月29日を「世界脳卒中デー(World Stroke Day)」とすることが宣言されました。
◇脳卒中とは?
脳卒中とは、脳の血管に障害が起こる病気の総称で、代表的なものに、血管が詰まる「脳梗塞」、血管が破れる「脳出血」「くも膜下出血」があります。脳梗塞や脳出血では意識障害や半身麻痺、言語障害等が、くも膜下出血では激しい頭痛や意識障害等が突然現れます。
最大の危険因子は高血圧で、糖尿病や肥満であることや、喫煙や飲酒などの生活習慣が発症に関わっています。体に負担のかかる生活習慣を続けていると、知らず知らずのうちに脳の血管が傷み、脳卒中を引き起こしてしまうのです。脳卒中は一命を取り留めたとしても後遺症が残ることが多く、主要な介護の原因にもなっています。
○脳卒中の症状といざという時の対応方法(長野県ホームページ)
https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/jyunkankibyo/symtoms.html
◇脳卒中は長野県の健康課題です
長野県において、脳卒中(脳血管疾患)は死因の第4位です(1位:がん、2位:老衰、3位:心疾患)。
長野県民の脳卒中における死亡率は全国に比べて高い現状があります。特に、男性の35-39歳、女性の55歳-64歳、男女の80歳以上の死亡率が全国より高い状況です。
脳血管疾患最大の危険因子である高血圧、あるいは血圧が高めな状態には、成人男性の約6割、女性の約5割が該当するという現状もあります。
◇予防するためには?
・適切な血圧管理を
まずはご自身の血圧を知ることから始めましょう。
135/85mmHgを超えることが続く場合は受診が必要です。
(参考:特定非営利活動法人 日本高血圧学会https://www.jpnsh.jp/pub_katei.html)
・塩分を控えた食生活を
次回のお食事はいつもより少し、塩分を気にしてみましょう。
(参考:長野県ゆるしお特設サイトhttps://ace.nagano.jp/yurushio/challenge/)
・適度な運動を
色鮮やかな紅葉が青空に映える季節になりました。お散歩に出かけてみませんか。
・特にリスクの高まる40歳を過ぎた方は、脳ドックを受診しましょう
(参考:一般社団法人 日本脳ドック学会 https://jbds.jp/brain-dock/)
・体や心を休める時間も大切に。
◆特にたばこは控えましょう
喫煙は、血管を傷つけ、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。
「今はまだ大丈夫」と思っていても、体の中では少しずつ影響が進んでいるかもしれません。
たばこを吸いたくなったら、仕事や気を張る場所から少し離れて、ストレッチや深呼吸をしてみましょう。気分転換の方法を見つけて、毎日頑張る体を労わってあげてください。
また今年は、望まない受動喫煙の防止を目的とした改正健康増進法の全面施行から5年の節目の年です。受動喫煙による健康被害を防止することが目的のこの法律は、特に子どもや治療中の病気がある方など、健康被害が大きい人々を守るためにより一層の配慮が求められ、屋内の原則禁煙や、喫煙場所の明確化、標識の掲示義務など、社会全体で受動喫煙を防ぐ取り組みが進められています。
この節目を機に、改めて「吸わない・吸わせない」環境づくりについても考えていただける機会となれば幸いです。
◎長野県の受動喫煙防止対策(長野県ホームページ)
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/kenko/kenko/kenko/tabako/jyudoukituen.html
明日、5年後、10年後のあなたが、ご自身と、そして大切なご家族やご友人、まわりの方々とありたい姿で一緒に過ごせるよう できることから始めてみませんか。
最初からすべてを我慢して、頑張らなければならないわけではありません。
小さな積み重ねが、未来のあなたの生活に繋がっていきます。
◇その一歩への情報はこちらから
長野県ゆるしお特設サイト:https://ace.nagano.jp/yurushio/challenge/
9月は「健康増進普及月間」です。
この月間は、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の重要性について理解を深め、一人ひとりの健康づくりの実践を促すために行われています。
令和7年度の重点テーマは「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 良い睡眠」です。
みなさん、普段の生活でからだを動かしていますか?
運動は、生活習慣病の予防や生活の質を向上させる重要な要素です。
運動は忙しくてなかなかできない、と感じている方もいらっしゃると思いますが、日常のちょっとした工夫でからだを動かすことができます。
長野県には、「ずく」という方言があり、「やる気」や「気力」といった意味を持ちます。
運動はできなくても、普段の生活の中で「ずく」を意識してからだを動かせば、立派な健康づくりになります。
たとえば・・・
・階段を積極的に使うこと(下りは特に効果的です)
・買い物は見て歩いて探すこと
・座りっぱなしが30分続いたら3分立つこと
など、「ずく」を意識して、普段の生活で今よりちょっと多くからだを動かしてみましょう。
長野県版身体活動ガイド「ずくだすガイド」(第2版)
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/kenko/kenko/kenko/undou/zukugaido.html
令和7年度健康増進普及月間 特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61544.html
この「健康増進普及月間」を機会に、「ずく」をだして、今よりも少しでも多く動くことを意識してみましょう。
仕事に育児に家事に…気づけば、今日も自分のことは後回し。
そんなふうに、毎日頑張り続けているあなたに。
ほんのひととき、自分自身にやさしく向き合ってみる時間を取ってみませんか。
1985年、日本心臓財団は8月10日を「健康ハートの日」と定めました。
「810(ハート)」という語呂にちなんだこの日は、私たち一人ひとりが“こころ”と“からだ”の健康について、立ち止まって考えるための日です。
日本では、心疾患が死因の第2位、脳血管疾患が第4位と、循環器の病気が多くの命に関わっています。
長野県では、心疾患が死亡原因の第3位、脳血管疾患が第4位です(令和5年人口動態調査より)。
さらに、県民の成人の半数以上が高血圧または血圧高めであることが分かっています(令和元年度県民健康・栄養調査より)。
高血圧が続くと、血管は硬くなり、心臓や脳の病気を引き起こしやすくなります。
予防・改善のためには、「健康的な生活」が非常に大切です。
「健康的な生活」と聞くと、「運動しなきゃ」「好きなものを我慢しなきゃ」と、ちょっと気が重くなるかもしれません。
でも、最初からすべてを我慢して、頑張らなければならないわけではありません。
○出勤時、出勤フロアの少し前の階でエレベーターを降りて、階段を使ってみる。
○いつものお弁当に、野菜を少し足してみる。
○お子さんと一緒に体を動かす時間を楽しむ。
〇いつもより少し早く布団に入って、ゆっくり体を休める。
そんな小さな積み重ねが、未来のあなたの生活に繋がっていきます。
また今年は、望まない受動喫煙の防止を目的とした改正健康増進法の全面施行から5年の節目の年です。受動喫煙による健康被害を防止することが目的のこの法律は、特に子供や患者など、健康被害が大きい人々への配慮が求められています。
日本心臓財団でよい生活習慣として提唱している「健康ハート10ヵ条」の中にも
「9 タバコは吸わない。頑固に禁煙。」とあるように、タバコを吸わないことが、心臓病だけでなく他のさまざまな生活習慣病のリスクを減らすことにもつながります。
あなた自身の健康はもちろんのこと、
あなたの大切な方達の心臓の健康も意識していただくきっかけになれば幸いです。
◎関連リンク
▶そもそも心臓ってどんな臓器?どんな病気があるの?
【「健康ハートの日」特設サイト】https://www.kenko810.com/heart_is_a_friend/
▶病気について、もっと知りたい
【一般社団法人 日本循環器協会HP】https://j-circ-assoc.or.jp/learn/
▶どんなことに気をつければ“健康ハート”を維持できる?
・【公益財団法人 日本心臓財団HP】
「健康ハート10ヵ条」 https://www.jhf.or.jp/topics/2014/000908/
・【一般社団法人 日本循環器協会HP】https://j-circ-assoc.or.jp/learn/
▶今すぐ実践できることを知りたい
【Youtube「信州ACEプロジェクト」チャンネル】
https://www.youtube.com/channel/UC4B1AWe48QVxf-dxQ1ht7ag
▶たばこに対する取組
・【長野県HP】
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/kenko/kenko/kenko/tabako/torikumi.html
・【厚生労働省HP】
「健康日本21アクション支援システム わが国のたばこ規制・対策の現状」
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/tobacco/t-04-004
長野県では、県民への運動習慣の定着を図るため、県民の皆様の生活スタイルに合わせ、日常生活の中で取り組みやすい身体活動の例を示した長野県オリジナルの身体活動ガイド「ずくだすガイド」を10年ぶりに改訂しました!
このガイドを県民の皆様に幅広く活用いただくため、下記のとおり指導者向け研修会を開催します。会場参加の方には、「ずくだすガイド(第2版)」をプレゼント!
健康づくりにご興味のある方、企業の健康管理担当者等、どなたでも参加可能です。
お近くの会場までぜひお気軽にお越しください。
【日時・場所】
〇 長野会場
令和7年6月30日(月) 13:30-15:00
県庁 講堂(長野市南長野幅下692-2)
〇 松本会場
令和7年7月24日(木) 13:30-15:00
松本合同庁舎 203号会議室(松本市大字島立1020)
【内容】
「ずくだすガイド(第2版)」の内容及び活用方法について(内容は2会場とも同じです)
【費用】
参加費は無料です。
【申込】
WEB申込フォームURL:https://forms.office.com/r/w0uAKjjdxs
なお、当該ページにアクセスできない場合は、別途ご連絡ください。
(申込期限:長野会場6月25日(水)まで、松本会場7月18日(金)まで)
その他、研修会の詳細等は県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/kenko/kenko/kenko/undou/zukugaido.html
チラシの記載内容の訂正について(お詫びとご案内)
信州ウォーキング大賞2025参加募集チラシの記載内容におきまして、内容に一部訂正すべき点が判明いたしました。
お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
【該当箇所】
「協会けんぽウォークの特徴」部分における「アプリのご利用は、下記のスマートフォンが対象となります。」に関する記載
【誤】Android6.0以上
【正】Android9.0以上
本件についてご不明な点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
全国健康保険協会長野支部
電話 026-238-1250
(音声案内「4」)
「健康で長生き」の実現に向けて、県民が自分に合った身体活動を見つけ、実践できるガイドとして平成26年3月に策定した「ずくだすガイド」を10年ぶりに改訂しました。
★県民に親しみやすいガイドとするため、初版と同様に方言である「ずく」の言葉をできるだけ取り入れています。山登りやスキー、雪かきなど長野県の豊かな自然や環境にあわせた動作もお示しして、より長野県らしく、より実践しやすい内容となるよう意識しました。
★日常生活で取り組んでほしい身体活動を「ずくのめやす」として紹介していますが、新たにライフステージ(成人/高齢者/こども)ごとに具体例をお示ししました。
 「ずくチェック」により、現在の身体活動状況やその意識や意欲の有無を確認することで、自分が「小ずくを出そう」「今より10分多く動こう」「仲間にも広めよう」の3つの段階のどの状態にあるかを把握するとともに、個々の状態に応じたおすすめの身体活動の具体例を知ることができます。
「ずくチェック」により、現在の身体活動状況やその意識や意欲の有無を確認することで、自分が「小ずくを出そう」「今より10分多く動こう」「仲間にも広めよう」の3つの段階のどの状態にあるかを把握するとともに、個々の状態に応じたおすすめの身体活動の具体例を知ることができます。
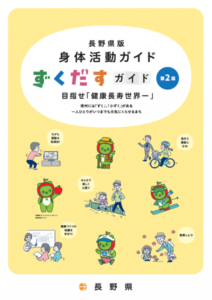 ガイド策定の意図や活用法を掲載しているほか、新たに情報源の二次元コードや解説のコラムを取り入れながら、身体活動の具体例や留意点等を解説しています。
ガイド策定の意図や活用法を掲載しているほか、新たに情報源の二次元コードや解説のコラムを取り入れながら、身体活動の具体例や留意点等を解説しています。
ガイドの詳細は下記からご確認ください!ダウンロードも可能です。
長野県ホームページ:長野県版身体活動ガイド「ずくだすガイド」
日時:2025年5月30日(金)16:00~17:30
会場:長野県高校教育会館 中会議室
(長野市県町593)
内容:○講演1 東京大学大学院総合文化研究科教授 中澤公孝 先生
演題「パラリンピックブレインにみる人間の可能性」
これまでのパラリンピックブレイン研究、ヒトの歩行研究で得られた知見から、
障がいの無い方にとっても重要な健康づくりの知恵(コツ)を教えていただきます。
○講演2 長野県立大学健康発達学部こども学科教授 前田 泰弘 先生
演題「幼児のからだとこころを育む野外保育」
発達障害幼児への野外保育の実践で得られた知見から、野外保育(外遊び)が、
幼児の動きや姿勢、感情調整の育みに好効果を及ぼす可能性についてお話しいただきます。
○講演3 立科町介護予防ドクター 鷹野 和美 先生
演題「「100歳ウォーキング ーいつまでも自立した生活をー」
寝たきりのいない国デンマークの視察から気づかれた一生ものの教育と実践、
それを産学官で実現している立科町の事例も紹介いただきます。
参加費:無料
申込:添付チラシ記載のQRコードからお申込みください。
定員:50名(先着)
詳細は添付のチラシをご覧ください。
(株)主婦の友社が雑誌「健康」の創刊50周年を記念し、新設した標記アワードで、長野県が初の受賞団体となりました。
1.アワードの概要
・主婦の友社が発行する雑誌「健康」創刊50周年を記念し、新たに創設
・人生100年時代を見据え、地域や企業、個人が取り組む「健康寿命延伸」の先進事例を表彰・発信するもの
・自治体では長野県を含む5道県を表彰
2.受賞理由
・健康長寿を目指す「信州ACEプロジェクト」を通じ、積極的な健康づくりの取組を様々な団体、個人等と一緒に進めている点
・健康寿命、平均寿命ともに毎年全国上位にランクインしており、健康長寿においてトップラスである点
・森林セラピー基地をはじめ、歩きたいと思わせるスポットやウォーキングコースが豊富な点
授賞式の様子等はこちら

働き盛り世代の皆様、長野県市町村国保加入者の40代の約40%、50代の約50%がメタボ該当者(予備群含む)であることをご存知でしょうか?
県では、市町村国保加入者にご協力いただき、健康管理アプリを使った食事・体重・運動について3ヶ月間記録してもらった結果を動画にしました。
記録した方の約75%が記録を続けることで食事や運動を意識するようになったという結果になりました。
「アプリに記録することで、健康意識が変わり、カラダも変わる。」
健康的な未来を目指すために、ぜひ動画をご覧いただき、メタボを始めとする生活習慣病の発症予防にお役立ていただければ幸いです。
「アプリで手軽に健康管理を始めよう!」
動画はこちら
動画は3分弱程度と短いものになっています。